マーケティング戦略においては、独自の立ち位置を確立するのは非常に有効な戦略の一つです。
特に、大量の情報があふれかえっている現代では、「ちょっとレアキャラ」になるのが重要です。
スモールビジネスにおいては、レアキャラになる必要はありません。
私たちは、「レアキャラって言うほどじゃないけど、周りにはあまりいないよね」というポジションを確立するのが大切です。
隣の街に同じようなキャラがいても関係ありません。
自分のテリトリーにいなければよいだけです。
その立ち位置を活かして、コンテンツマーケティングを実行することは、スモールビジネスを成功させるうえで有効な手段になります。
コンテンツマーケティングとは
コンテンツとは、簡単に言えば、「本とか映像の”中身”」のことを指します。
具体的には次のものが挙げられます。
- 文字コンテンツ:本、ブログ、レポート
- 映像コンテンツ:動画、アニメ、スライドショー
- 音声コンテンツ:音楽、ラジオ、ポッドキャスト
- 画像コンテンツ:写真、イラスト、図
- インタラクティブコンテンツ:ゲーム、クイズ、デモ
では、コンテンツがマーケティングとかけ合わさるとどうなるのか。
コンテンツマーケティングは、次のように定義されます。
「コンテンツマーケティングとは、ターゲットユーザーに付加価値を提供するための有益な、関連性のある、一貫したコンテンツを作成・配信するマーケティングアプローチのことです。
このアプローチの主な目的は、最終的にターゲットユーザーを顧客に変えることを目指すことです。」
従来のマーケティングは、広告というものが大きなウェイトを占めていました。
テレビ・ラジオ広告、雑誌広告、屋外広告、ダイレクトメール(DM)など、多くのマーケティングは広告を中心に組み立てられていました。
広告では、基本的には宣伝する側のメッセージが伝えられ、短期的に商品購入につなげるのが目的でした。
そういった中で出現してきたコンテンツマーケティングとは、「ユーザーに有益なモノ(コンテンツ)を提供することで、お互いの信頼関係をつくり、ビジネスにつなげる」という手法です。
特にWebと親和性が高いのも特徴です
例えば、次のような事例が挙げられます。
- 地元カフェのブログ活用
地元の食材を使用したレシピや、店主の地元愛についてのブログを掲載。
これにより、地域コミュニティとのつながりが深まり、店への来店者が増加。
特に地元のユーザーから人気となっています。 - 手作りアクセサリーショップのSNS活用
製品の製作過程、製品への想い、使い方の提案などをInstagramで定期的に発信。
フォロワーとのやり取りを通じて、エンゲージメントが向上し、SNS経由での商品購入や、口コミによる新規顧客の獲得が増加しました。 - 地域密着型の不動産会社による地域紹介
YouTubeチャンネルを開設して、取り扱っているエリアの魅力や生活情報、観光スポットなどを紹介する動画を公開。
エリアへの移住や賃貸を検討している人々に有益な情報を提供することで、信頼関係の構築と同時に、不動産取引の問合せ獲得にも繋がりました。
コンテンツマーケティングのメリットとデメリット
メリット
コンテンツマーケティングのメリットは、次に挙げる通りです。
また、長期的に効果が持続することがポイントです。
- ブランドの認知向上
- 顧客との長期的な信頼関係の構築
- 長期的に継続されるSEO効果
デメリット
逆にデメリットは以下の通りです。
長期的な効果が表れやすい分、手間暇がかかります。
- 時間と労力がかかる
- すぐに成果が出ない
- 継続的なアップデートが必要
- 試行錯誤が必要
- 競合が多い
コンテンツ戦略とコンテンツマーケティング戦略の違い
2つの言葉は似ていますが、位置づけや目的が違います。
コンテンツ戦略とは
コンテンツ戦略は、主にコンテンツの作成、公開、管理、最適化に関する方針やガイドラインを中心にしています。
「どのようなコンテンツを、どのターゲットオーディエンスに、どのタイミングで提供するか」、そして、「そのコンテンツがどのようにビジネスやブランドの目的をサポートするか」に焦点を当てます。
コンテンツマーケティング戦略とは
コンテンツマーケティング戦略は、特定のマーケティング目的や目標を達成するために、コンテンツを使用してターゲットオーディエンスを引き付け、エンゲージメントを促進し、最終的にはコンバージョン(たとえば売上目標)を達成するためのアプローチです。
あくまで、売上目標を達成するための手段です。
顧客の購入旅行を通じてのエンゲージメントの向上、リードジェネレーション、顧客のロイヤリティ強化など、マーケティングの具体的な目的を達成するためにコンテンツをどう活用するかに焦点を当てます。
ピリッと光るコンテンツマーケティング戦略
コンテンツマーケティングで成功するには、戦略が重要です。
「戦略なきは座して死を待つがごとし」です。
具体的には、まずは下記の事項を十分に検討しましょう。
完璧に決める必要はありませんが、おおむねの方針が決まるまでは、実行はストップです。
- 目的を明確にする
まず、何のためにマーケティングを行うのか、目標を明確にします。
たとえば、ブランドの認知向上、問合せの獲得、顧客エンゲージメントの強化などが考えられます。
- ターゲットユーザーをよく理解する
ユーザーが何を欲しているか、どんなことを望んでいるかをよくよく考えてみます。
具体的にペルソナをつくってみると分かりやすいです。
- どういった価値を提供するか
ターゲットユーザーがイメージできると、どんなことを知りたいと思っているかが少し理解できます。
それに合わせて提供できる情報や解決策を考えてみます。
ターゲットユーザーになりきってみて、どんなものだったら欲しいと思うか、考えてみることが重要です。
仮にお金を払ってでも欲しいと思えるかを考えてみるのも良い方法です。
- 質の高いコンテンツを作成する
これは重要であるにもかかわらず軽視されがちです。
ついつい、コンテンツを量産したくなりますが、ひとつひとつの質が低いとつくっても意味がありません。
手を抜いてつくったものは、誰にも評価されません(SEOの効果も薄いです)。
自分のできる限りのエネルギーを注いで作ることが大切です。
- 掲載メディアを選ぶ
ユーザーによってアクセスしやすいメディアが違います。
Twitterが好きな人もいますし、YouTubeで動画を見るのが好きという人もいます。
自分がユーザーだったら、どんなものを利用するかをイメージしてみることが重要です。
- 定期的に更新する
情報の鮮度を保つために、定期的に更新することが大切です。
- ユーザーとやりとりをする
コンテンツを通じて、ユーザーとやりとりをすることも大切です。
ユーザーの投稿にコメントをしたり、アンケートを収集して意見を聞いたり。
ただし、ユーザーには敬意をもって接しましょう。
- 人気コンテンツを分析する
どのコンテンツがよく読まれているかを分析して、必要に応じて方向性を修正します。
たとえば、コーヒー豆のマメ知識についてのコンテンツが見られているのであれば、他のマメ知識コンテンツを作成してみるのもありです。
- 計画を立てる
事前にある程度の計画を立ててから、コンテンツを作成します。
必要なお金や、制作期間、配信するメディアなどは要検討です。
- 継続する
コンテンツは作成して終わりではないです。
継続的に新しいものをつくったり、改善をしたりする必要があります。
継続的に価値を提供することで、ブランドの信頼性が高まり、ユーザーとの関係性が深まります。
現実には、やりながら修正していく部分も多いです。
「8割は決めて2割はやりながら考える」のがよい方法です。
大事なのは、ブレない軸だけは決めておくことです。
- 戦略が一番重要
- ターゲットユーザーを理解する
- ブレない軸を決める
重要なのはターゲットユーザーの理解
一番初めにやるべきで、なおかつ非常に重要な作業が、ターゲットユーザーの理解です。
これができれば8割は達成したようなものです。
具体的には、次のような方法があります。
ただ、基本は「実際に現地まで行く」、「ユーザーに聞く」、「自分で使ってみる」です。
- 現地に行ってみる
- 実際のユーザーや周囲の誰かに聞く
- 自分で使ってみる
- (信頼できる)ネット記事や調査レポートを読む
- 競合となる企業のWebサイトを深く読む
- 頭の中で想像してみる
- (あくまで参考までに)SNSをチェックする
SNSやネット情報は、参考になることも多いですが、玉石混交です。
やはり、リアルの情報が一番大切です。
「ちょっとレアキャラ」になる
とはいえ、現代では大量の情報があふれかえっています。
たとえば、ネット上には同じような記事コンテンツがたくさんあり、差別化は簡単ではないです。
そのような状況において重要な戦略は、「自分の経験に基づいた情報を発信する」と、「ある領域において唯一の存在になる」です。
人間はだれしもが自分だけの経験を積み重ねて歳を重ねます。
ひとつひとつの経験は色々な方が経験しているものですが、それらを組み合わせると、他の誰もが経験したことのない貴重な経験となります。
そして、多くの人は自分の経験を発信してはいません。
有名な方の情報発信がメディアを賑わせますが、それはごく一部の人気者です。
ほとんどの方はメディアに現れることなく、日々を過ごしています。
たとえば、私は中小企業でマーケターをしていますが、そもそも中小企業でマーケターをやっている方は多くありません。
また、情報発信をしている人も少ないはずです。
情報発信をしているけれども、あくまで企業として情報発信をしているという人もいるはずです。
そうすると、「中小企業×マーケティング×個人、というかけ合わせの中では、”ちょっとレアキャラ”」です(唯一ではないかもしれませんが)。
しかも、大手広告代理店を経験して、中小企業の事業会社に移るという経験もあまり多くの方が経験しているものではもないかもしれません。
このように、「いくつもかけ合わせることで”ちょっとレアキャラ”になる」ことができます。
ちょっとレアキャラになって、自分の貴重な経験を発信するのは、狭いテリトリーであればあまり真似はできません。
まずは、ひとつずつは大したものでなくても、色々かけ合わせてみましょう。
- 自分の経験に基づいた情報を発信する
- ある領域で唯一の存在になる
- かけ合わせて「ちょっとレアキャラ」を目指す
生成AIの利用について
近年、Chat GPTなどの生成AIが活用されています。
コンテンツマーケティングにおいても利用しない手はありません。
ただ、たとえば「カフェに関する記事を書いて」とお願いして、Chat GPTにすべて書いてもらうのはNGです。
たしかに、Chat GPTは大変優秀で、おおむね正しい記事を書いてくれます。
実はこの記事もChat GPTを活用して書いています。
しかし、Chat GPTへの規制は今後間違いなく強まるため、自動で生成されたコンテンツへの評価は高くはなりません。
少なくとも現時点では、長期的にメリットのあるコンテンツを生成することは難しいです。
現状では、まだ人間に分があり、手間暇をかけて作成したコンテンツは、高く評価される可能性が高いです(そのうちなくなる可能性もありますが(笑))。
そのうえで、Chat GPTの有効な活用方法は、「相談しながら一緒にコンテンツをつくる」ことです。
たとえば、次のような活用方法があります。
- コンテンツ向けのネタを提供してもらう
- つくった記事コンテンツの校正をしてもらう
- ざっくりした事例情報をもらう
- 意見をもらいながら、ネタをブラッシュアップする
- 構成案をつくってもらう
正直なところ、Chat GPTに「記事を書いて」といえば、書いてくれます。
ただ、部分的に不自然さがあり、正しいのだけれど、ごく一般的な情報というイメージです。
なので、全面的に頼るのではなく、「パートナーとして頼る」のが最適な方法かと思います。
- コンテンツマーケティングで重要なのは戦略
- ターゲットユーザーをイメージする
- 生成AIはパートナーとして頼る
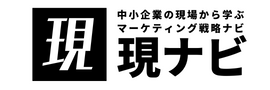
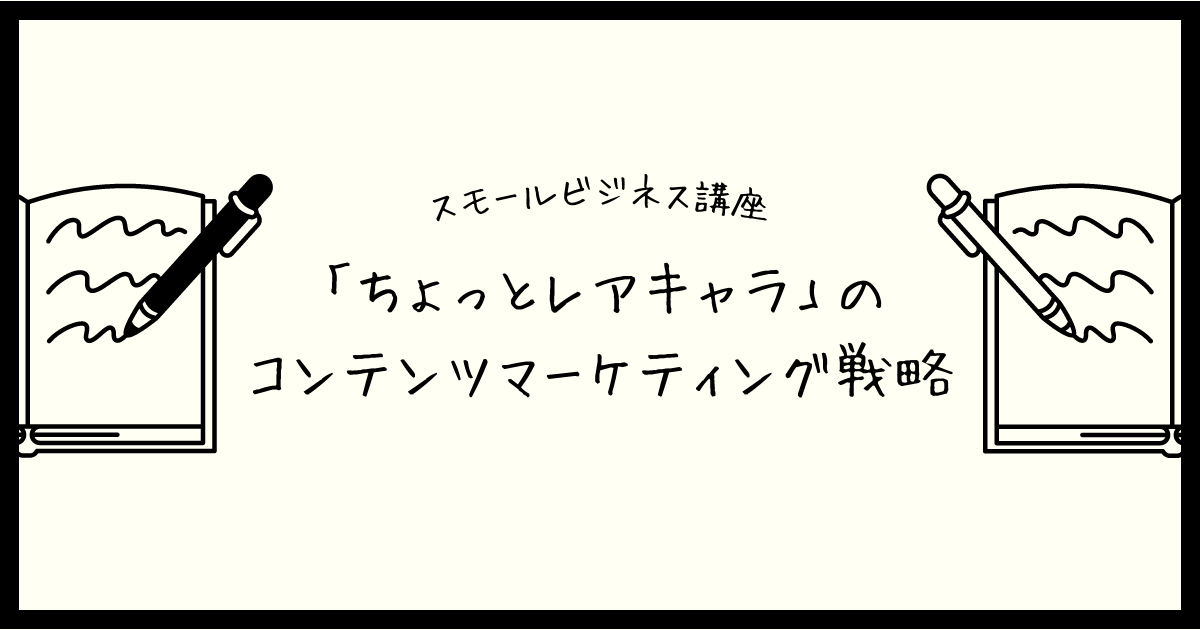
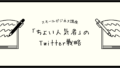
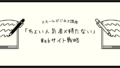
コメント